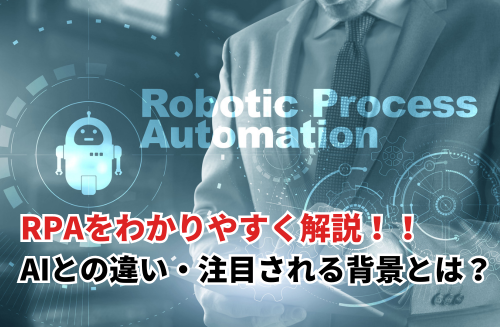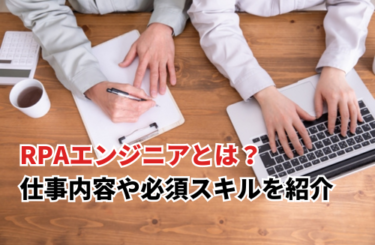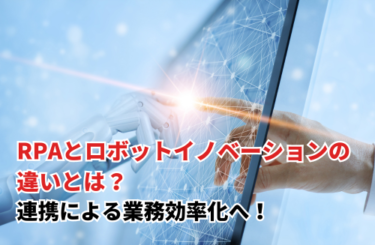業務の効率化や生産性向上を実現するためにRPAを導入する企業が増えており、RPAという言葉をメディアで見る機会も増えました。
競合他社がRPAを導入しており、自社でもRPAの導入を検討している企業もいるのではないでしょうか?
しかし、実際にRPAについて「詳しくわからない」「AIと何が違うの?」と疑問を抱えたままRPAを導入しても効果的に使用できません。
そこで本記事では、RPAの基礎知識からAIとの違い、生産性向上に最適な業務など詳しく解説していきます。
RPAの導入について詳しく知りたい方は下記記事をご覧ください。
業務効率化や生産性の向上を目的にRPAを導入している企業が増えています。 ニュースや他社の導入事例を見て「自社でもRPAを導入しよう!」と検討している企業も多いですが、RPAの導入は簡単ではありません。 導入の進め方や手順を怠ると、[…]
RPAとは?

RPAとは、「ロボティック・プロセス・オートメーション(Robotic Process Automation:ソフトウェアロボットによる業務自動化)」を略した言葉です。
RPAツールと呼ばれるソフトウェアを利用し、パソコン上で行う定型業務を自動化する技術です。
パソコン内で完結する業務プロセスを一度登録すれば業務を全て代行できるため、単純作業と相性が良いとされています。
また、定型業務は手作業で行うよりRPAで自動化した方が、ミスもなく素早く仕事を行なってくれるため多くの企業が導入しています。
RPAとAIの違い
似たようなものとして説明されるRPAとAIですが、大きな違いがあります。
RPAは人間が設定したルールに従って動きますが、AIは人間と同じような知能を持たせるため学習を行い自己判断も行います。
例えば、自社で新しい商品を作るとします。
その際にRPAは「ネットの情報から他社の分析」「消費者の購買の傾向」などを見てデータ化しますが、その後の新商品のアイデアは人間が考えなければなりません。
一方、AIはデータの規則性を見出し、より売れる商品の傾向やこれから人気になる商品のアイデアを提案してくれます。
イメージとしてRPAは「手」、AIは「脳」の役割と考えましょう。
| 主な業務範囲 | 具体的な作業範囲 | |
| AI | 高度な自律化 | ・情報取得 ・プロセスの分析 ・意思決定など |
| RPA | 定型業務の自動化 | ・情報取得 ・ルール化された作業 ・検証作業など |
RPAが注目される背景

RPAが注目されている背景は、新型コロナウイルスによる「労働環境の変化」と「働き方改革」により、注目を集めたと考えられています。
では実際にどんな変化があり、RPAが注目されたのでしょうか?以下3点を踏まえつつ詳しく解説していきます。
- 労働時間の改善
- 人手不足の解消
- コストの削減
労働全体の改善
働き方改革を掲げて、労働改善の見直しが大きく注目を集めました。
特に「有給取得」や「残業時間の減少」は改善せざる得ないものとして、企業も改善を余儀なくされました。
有給取得率を上げるためには、業務の効率化を測り生産性を上げなければなりませんし、残業時間の減少は今まで残業で賄っていた業務をなんとかする必要があります。
RPAであれば、業務の効率化を上げることができ24時間365日稼働できるため「有給取得」や「残業時間の減少」を抑えることができ、労働全体の改善ができるため導入企業が増加しました。
人手不足の解消
人手不足が深刻となりつつあるいま、人材確保は大きな課題となっています。
自由な働き方を求める人が増えてきており、優秀な人材を確保することが難しく人材を確保できたとしても現場へ降りてくるまでに時間がかかるため企業全体の生産性向上にも時間がかかります。
こうした問題を解決するための方法としてRPAへの関心が高まったとされています。
RPAは一度仕事を覚えさせれば即戦力にもなる上に、1台のロボットで何人分の働きをしてくれます。生産性向上にも時間がかからないため人手不足が深刻になりつつある現代では貴重な存在といえます。
コストの削減
企業が常に抱えている課題としてコストの削減があります。
特に企業が大規模になればなるほど、人を雇い人件費を払わなければなりませんが大きなコストとして経営者を悩ませるものです。
こうしたコストの削減にもRPAが注目されています。RPAは導入費用こそ高いものの一度導入をしてしまえば、ランニングコストのみで稼働させることができます。
また、従業員の長時間労働や残業の心配もないのでコストの削減に大きく貢献するとされています。
RPAの導入で効率化できる業務

パソコン内でできる業務がRPAが全てできるわけではありません。
RPAには得意・不得意な業務があります。ここからはRPAが得意としている業務以下4点を紹介します。
- 他社の調査
- 顧客情報の管理
- 問い合わせ対応
- 人事・勤怠管理
他社の調査
競合他社の調査は多くの企業にとって重要な業務です。
しかし、常にネットの情報を見ておくにはかなりリソースがかかり、分析などを行うと作業コストも大きなものになります。
また、分析を常に行なっていたらモチベーションの低下にもつながり、ミスを起こす可能性もあります。
RPAであれば、24時間常に最新の情報を取得でき分析も行えるため、他社の動向をチェックすることができます。ミスの可能性もないので、正確な情報を逐一チェックすることができます。
顧客情報の管理
顧客情報の管理は重要な業務であるとともに、情報が外部に漏れてしまうと大惨事になりかねません。
顧客の管理は多くの企業が「顧客管理システム」や「Excel」で管理し、手入力で情報を入力します。数が多くなればなるほどコストがかかるとともに、管理に大幅なコストがかかります。
RPAであれば顧客の情報入力、検証、更新など繰り返し行われる作業を自動化することができ、顧客の情報を安全に管理することができます。
問い合わせ対応
LINEやメールなどを利用し、顧客にお問い合わせを対応している企業も多いかと思います。しかし、一通づつ返信するのはかなりのコストがかかります。
RPAではLINEやメールの返信に対して自動で返信を行うことができ、質問と回答を事前に用意しておけば定型文を送ることが可能です。
また、チャットボットと組み合わせをすることでより効率化できます。
人事・勤怠管理
人事・勤怠管理はRPAで効率的に行うことができます。
多くの企業では、出退勤の打刻を勤怠管理システムで行い、打刻漏れがあった場合には勤怠管理をする部署から打刻申請通知を行います。
しかし、勤怠管理では多くの従業員を管理すると、ミスを起こしやすく作業コストもかなりかかります。
こうした人事・勤怠管理はRPAで管理することで打刻漏れも常に監視でき、すぐに通知を飛ばすことができます。また、従業員1人1人の残業時間もチェックできるので、過剰労働を行なっている従業員も知ることができます。
RPAの導入をおすすめする業種

前述した業務は実際にどのような業種で活用できるのでしょうか?
ここからはRPAが活用できる業種以下5点を詳しく解説します。
- 製造業
- 営業
- 物流業
- 不動産業
- 人材業
製造業
製造業は工場での、加工や製造が強いイメージですが事務作業も数多く存在します。
例えば、製造業では「測定結果の転記」を行う必要があります。
工場で製作した製品の精度検査結果をシステムに記録するため、検査担当者がシステムに手動で入力する必要がありました。この作業は膨大な時間がかかる上にミスを起こしやすい作業です。
RPAであれば、AI-OCRと組み合わせることで測定結果をシステムに読み込み自動で入力を行うことができます。人間が行うのは入力された検査結果の最終チェックのみですので、作業コストをかなり短縮できます。
営業
営業職業務では、
- 膨大な顧客の管理
- 競合他社の価格調査
- 請求書の作成
- 営業レポート作成
など事務作業は膨大です。
例えば、請求書の作成は取引先に送りますが価格が間違っていれば会社の売上にも関わります。
また、営業レポート作成も毎日の提出が決められていることも多く1年を通せば膨大な作業時間がかかります。
RPAはこうした作業を全て自動化してくれるため、ミスを防ぐことができ営業に集中して行うことができます。
物流業
物流業では「在庫管理」や「受発注書業務の作成」など事務作業が発生します。
特に在庫管理は商品が多くなればなるほど、人員を増やす必要があり連携が取りづらくミスを起こす可能性も上がります。
こうした在庫管理もRPAでは全て管理することが可能です。すぐに在庫の個数をチェックできるため、在庫が不足することもありません。
また、RPAとチャットボットを連携させることで、
- 顧客がチャットボットで商品の検索
- RPAに商品名で反応するように登録しておけば、在庫を反映
- 顧客が在庫を確認
こうした一連の作業の自動化もできます。
不動産業
不動産業では、物件の情報を素早く取得しネット上で反映させなければいけません。
しかし、常にネットをチェックしておくことは難しく通常の業務にも支障をきたします。
RPAであれば常に最新情報をチェックすることができ、物件の反映も可能です。
最新の物件のチェックも行うことができるため、会社の売上・生産性の向上も期待することができます。
人材業
人材業界では、膨大な求人情報・個人情報を管理する上に企業・個人とのコミュニケーションコストも発生します。
RPAであれば、求人募集している企業や求職者との連絡を自動化し、登録した求職者の情報入力も全て自動化できます。
近年では労働者不足のため、スカウトメールを送信する企業も増えていますが、RPAで送信することができます。
人材業界で疎かになりがちな求職者の支援を重点的に行うことが可能になります。
より詳しく業種・業務別に活用方法を知りたい方は下記記事を合わせてご覧ください。
働き方改革の推進にともない多くの企業がRPAを導入し、社内の働き方を改善しています。 しかし、実際にはRPAを導入しても、効果的な使用ができず業務の効率化が上手くいっていない企業も多いのではないでしょうか? そこで本記事では、実際に[…]
RPAの将来性は?

RPAは年々需要が高まっており、これからも導入する企業が増加すると言われています。
その理由として挙げられるのが、労働人口の減少です。
厚生労働省の調査によると2030年に人口は約1,1億人まで減少すると見込まれており、人口の減少に伴い労働人口も減少すると考えれています。人材の確保が難しくなるため、RPAを導入せざる得ない事態になる企業も出現し多くの企業がRPAを導入すると考えれられます。
RPAによる業務効率化・生産性向上に乗り遅れないためにも、これからRPAの導入を検討している企業は、ぜひ本記事を参考にしてください。